嘉納治五郎の柔道と教育6 なんとかなるわい。
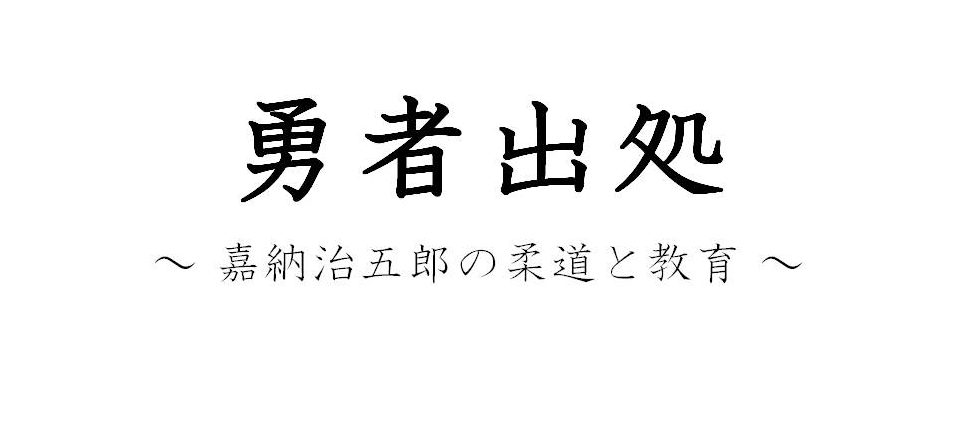
※以下は、2010年8月から酒井重義(judo3.0)によってブログで連載された研究論考「勇者出処~嘉納治五郎の柔道と教育」の再掲です。
「精力善用」というコンセプトは、武術から教育、仕事、衣食住、経営、読書など、ありとあらゆる場面に妥当する原理であるが、精神状態にも妥当する。つまり、如何にうまく行うか、というdoingの場面だけではなく、どんな態度、スタンスで日々を過ごすか、というbeingの場面にも妥当する原理である。第6回では、このbeingにおける精力善用についてみていきたい。
己の過失
もし、柔道を修めたものの中に、いたずらに己の過失を悔い悲しむものがあるならば、それは未だ柔道の奥義を解した者ということは出来ぬ。過失は過失として自覚することは、もとより願わしいことである。しかし、過ぎ去った過失について、いたずらに後悔悲歎しても何の益もない、むしろ、過失たることを認めたる以上は、再び同様の過失を繰り返さぬようにし、如何にすればその過失を贖うことが出来るかということを考慮し、出来るだけ努力してよい事をしようとし、寸隙も無用の事に精力を費やさぬように心掛けなければならぬ。
忿怒
また、柔道を解している者は、みだりに忿怒することはないはずである。憤怒することは、情性が理性を支配して人が冷静の精神状態を失った時に生ずる現象である。憤怒して何の益があるか、多くの場合は、己の精力を余分に減損し、他人に不快を感ぜしむるかまたは嘲笑せらるるのが落ちである。
不平
不平をいうこともそうである、不平をいうて己を益しまたは他を益するところもない。そういうことをしている閑時間があるなら、己の為すべきことを遺漏なく為し遂げ、再び不平の起きる原因除去するに越したことはない。
煩悶
煩悶というようなことも同様、柔道の精神的修養の出来た者には生じないことである。一体、人は何を煩悶するであろう。煩悶はいくらも行く途がある、どちらを行こうかと迷う場合に生ずる精神状態であるが、本来柔道の教えでは、一つしか行く途はないのである。心身の力を最も有効に使用するということが柔道の教えである以上、一番よいと思う事をしさえすれば、それでよいのである。世が毎々いうように、人生行路唯有一耳の八字がこの意味を尽くしている。
ある人は、それでも最善の途がいずれか分からぬ時はどうするか、と難ずるかも知れぬが、それは、ひととおり考えをしなければならぬ場合はある。しかし、考えるのと煩悶とは違う。そして、その考えることも、大抵の場合そう長い時を費やす必要のあるものではない。
あたかも旅行する時岐路があって聞く人がなかったら、人は何時間とか何日間とかいう程立止まって煩悶しているか、そういうことはあるまい。必ず一考した上、まずこれであろうと考えた方を選んでその方へ行き、それが間違っていたならば、その場合に新たに判断して正しいと思う方向に進むであろう。何も煩悶している必要はない。それと同じように、すべての事は解決されるのである。
柔道を修めている者は、せめて以上述べたような単純なことでは無用の苦しみをして貰いたくないのである(以上、嘉納・著作集2巻90頁)
人間の進むべき道
かく如何なる場合に当たっても人間の進むべき道はただ一つである。いつでもその場合においてどうするのかが最も適当であるかを考究し、その方向に進むというのが唯一の道である。自分は一つの語を作って平素人に示している。「人生行路唯有一耳」というのがそれである。この主義で日常己の身を処して行くのが最も必要である。
人間が成功の絶頂に立った時も、進むべき道はただ一つである。すなわち安心しては失敗の源の醸することになるから、あくまで慎重に考慮し、最も適当な道を見出してその方向に進むことである。
また、失敗の極点に立っても進むべき途はただ一つである。一度は失望落胆しても、勇気を取り直して進むべき最上の道をたどれば、たちまち前途に光明を認めその境遇は漸次よくなる。どこにも探求すれば最善の道はある。
それにかかわらず、失望し落胆したぎりで自暴自棄するという法はない。如何なる時にもその進むべき最善の道がある。そしてそれは、現在を改善して、前途に光明を与うるところの道である。人は勇み立ってこの道を取り、精力を尽くして一層よき状態に達しなくてはならぬ。
要するに、精力最善活用主義を奉ずるものは、己の進むべき道を見出すが故に何時でも心が安穏で、楽しく進取的である。人間の最も進んだ精神生活は、この主義を徹底的に体得した者によって始めて営まれ得るのである(嘉納・著作集2巻260頁)。
「なあにッ」
それでは、「人生行路唯有一耳」と思われる嘉納のエピソードを二つあげる。
東急電鉄を創った五島慶太氏(五島慶太 – Wikipedia)は、高等師範学校で嘉納の修身科の講義を受けているが、次の話が忘れられないという。
高師では1週間に1回、この嘉納校長の修身科があった。その講義の変わっていることは、はじめからしまいまで「なあにくそッ」の一点張りで、ほかのことは何も説きやしない。これは柔道の方から来た不屈の精神の鼓吹で、勝っても「なあにッ」、負けても「なあにッ」、どっちに転んでも「なあにッ」という訓えであった。
私も最初は、へんなことをいう先生だなと思っていたが、これを1年間繰り返し聞かされているうちに、なるほどとだんだんわかり出してきた。しかし、体験的には、まだまだよくわかりきらなかった。
ところが、世の中へ出てみて先生の訓えが本当にわかった。高師ではむろん英語とか、地歴とか、教育学とか、いろいろなことを教わった。それらの大方は忘れてしまった今日まで、一番頭に残り、一番役に立ったのは、この「なあにくそッ」であった。どんなことにぶつかっても、これさえ忘れなければ必ずやっていける、という先生の言葉はうそではなかった(加藤仁平・嘉納治五郎5頁)。
筆者は、この話を聞いたとき、池田潔氏の『自由と規律』(岩波新書)にある、英国のパブリックスクールのあるホールに勤務していたという、競馬好きの老給仕人ジョージの話を思い出した。
嘉納が生きた時代とは、パクス・ブリタニカ(パクス・ブリタニカ – Wikipedia)と評される時代であるが(嘉納が数え年43歳のとき日英同盟が締結)、この大英帝国の教育制度、とりわけ私立の中等学校であるパブリックスクールは、世界一等の中等教育機関であった。ちなみに、このパブリックスクールにおけるスポーツ教育が大英帝国の力の源泉であるとし、それをフランス及び世界に普及しようと企図した者が、オリンピックを創ったピエール・ド・クーベルタン(ピエール・ド・クーベルタン – Wikipedia)である。
さて、池田潔氏は、パブリックスクールに在学した記憶を回想しながら次のようにいう。
あるカレージのホールに、ジョージと呼ばれる老給仕人がいた。身体のずんぐり肥った、首の太い、鼻先きと両頬が熟した李のように暗紫いろに色づいた、亜麻色の泥鰌髭を生やした男だった。いったい幾歳になるのか、もう何十年ここにいるのか、誰も知らなかった。ついぞ人に笑顔を見せたことがないといわれ、学生とは勿論、仲間同士でもあまり話をしている風はなかった。その男が、一年に何度かそのようなことがあったのだが、何かの拍子に興にのって、ポツリポツリと語りだすことがあった。
最近四、五十年間にこの学校を出た人達の言動や逸話に例をとった、いわば人生哲学の講釈だったのだが、これは決して誰でもが聞けたのではなく、限られた少数者にのみ許された特権とされていたのである。そしてこの講釈は、この町の日曜の昼の寺の音とともに、一度きいたものの胸に、妙にいつまでも遺るのであった。
競馬好きのジョージによれば、人間はすべて先天的に駿馬か駄馬かに決まっている。その相違がはっきり示されるのは、勝負事に負けたときの態度である。駿馬は負けても顎を落とさない、悪びれた様子を見せない。社会的地位や経済環境が変わっても、駄馬が急に駿馬には化けられない。白猫にペンキを塗っても三毛猫にならないのである。自分は駄馬には用はない。運動場で見ていると実に駄馬はよく判るのだが、貴重な時間と学費を空費して、何のためにあの連中が学校にいるのか(161頁)。
嘉納と老給仕人ジョージは同じ時代に生きているから、嘉納がパブリックスクールを訪問したとき、もしかすると、嘉納はジョージを見かけていたかもしれないが、「勝っても「なあにッ」、負けても「なあにッ」、どっちに転んでも「なあにッ」」という嘉納は、疑いなく駿馬だろう。
「なんとかなるわい。」
最後にもうひとつエピソードを。
東京大学教授の宗像誠也氏(宗像誠也 – Wikipedia)の父は、嘉納に学んだ人であり、先生(嘉納)なくしては父は考えられないという関係にあったというが、宗像氏は、次のようなエピソードを話している。
今はもう時効にかかっているから書いても先生の御名誉を傷つけることもあるまい。父の畝傍時代、先生がお仕事の関係で誰やらから金をお借りになった時、父は保証人の判を捺したが、催促を受けても払えず、父の許にまで差押えが来た。父は校長たるの地位にも関係すると思い、あわてて状況して先生のお宅に推参したが、先生は家財道具も運び出されてガランとした邸内に一人おられて、父の泣訴に対してただ一言「なんとかなるわい」といわれたという話。誠に失礼だが対照がはっきりしていて面白くてならぬのである(加藤仁平・嘉納治五郎257頁、楽善抄77~78頁)
筆者が読んでいる文献は非常に限られたものであるが、この「先生は、家財道具も運び出されてガランとした邸内に一人おられて、父の泣訴に対してただ一言「なんとかなるわい」といわれた」という話は、筆者が最も好きなシーンの一つであり、このシーンに思いをはせるだけで元気がでる。嘉納は、講道館、清国留学生の教育、日本のオリンピック参加など、いずれも創業者として多額の借財を背負い「筆舌に絶する」苦労(加藤仁平・嘉納治五郎258頁)をしたというが、このことはいずれ機会があれば触れたい。
この苦労をした嘉納が、「あたかも旅行する時岐路があって聞く人がなかったら、人は何時間とか何日間とかいう程、立止まって煩悶しているか、そういうことはあるまい。必ず一考した上、まずこれであろうと考えた方を選んでその方へ行き、それが間違っていたならば、その場合に新たに判断して正しいと思う方向に進むであろう。何も煩悶している必要はない。」と言うのである。元気が出る話だと思うが、いかがだろうか。










