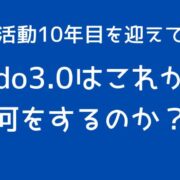嘉納治五郎の柔道と教育23 生き方の基本は、伝統とのかかわりの中で見出すべき1
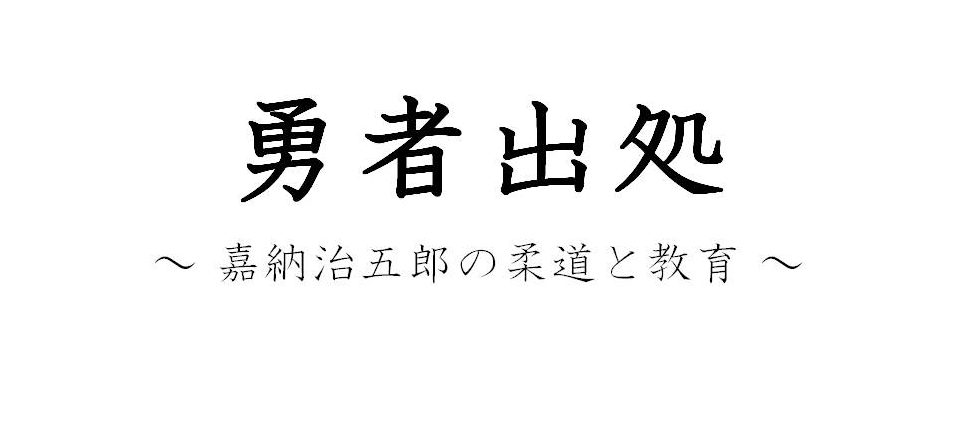
日本の文化・伝統にふれる理由
今回は日本の文化・伝統についてみていくが、その前に、何故、この点を考察するか、その意義をまず明らかにしておきたい。
本稿は、柔道の教育としてポテンシャルを最大化することを目的とし、「短期的目標」と「長期的目標」のバランスが重要であるという枠組で検討している。
短期的目標とは、試合に勝つ、柔道の技術を学ぶなどであり、長期的な目標は、「精力善用・自他共栄」という大道を身につけそれに基づいて生きること、「己を完成させ世を補益すること」、人間的に成長し社会に役立つ人間になることなどであり、いうなれば、短期的目標は「技術」の領域、長期的目標は「生き方」の領域の話である。
この「生き方」について、倫理学者の相良亨氏は、私たち日本人は「日本の伝統の中に生れ生きているのであって」「人間いかに生きるべきか」という問題は、「まさにこの伝統を根底にふまえたものでなくてはならない」、
そして、「日本人が精神的な安定をもって生きるためには、まず、われわれの生き方の基本は、われわれの伝統とのかかわりの中に見出すべきものと腰を落ち着けることであり、伝統の昇華の中に、精神のよりどころをしかと把握していくことである」という。
そして、斉藤孝氏が指摘するように、実際に、嘉納は、日本の「武」の内包されていた人間形成の文化を見出し、それを日本のみならず世界に広めた(前回参照)。
つまり、嘉納は、「柔術」という日本の伝統とのかかわりの中で普遍的な「生き方の基本」を見出したのであり、それを世界に広めたといえる。
したがって、嘉納の柔道の「長期的目標」を深く理解するためには、嘉納が日本の文化・伝統の中に見出した普遍的なものは何か、という点をみていくことが必要なのではないか。これが、今回、日本の文化や伝統にふれる理由である。
「道」
もっとも、一口に日本の文化・伝統といっても広大すぎる。そこで、「道」という言葉に内在する日本の思想を考察した相良亨氏の著書『日本の思想―理・自然・道・天・心・伝統』を参考にし、「道」に内包する三つのコンセプトにふれた後、柔道と教育について3点ほどコメントしておきたい。
なお、言うまでもなく「道」という言葉は、「柔道」「講道館」と命名されたとおり柔道にとって重要な概念であり、また、いわゆる「芸道」(芸道 – Wikipedia)と称されるように、書道、茶道、弓道、剣道、など諸芸に付されるものである。
個々から普遍へ
「道」に含まれるコンセプトとして第一に挙げられるものは、ある特定の個々の領域における究極的な境地が、その領域を超えて宇宙や人間そのものの究極的な境地につながる、というものである。同時にこれは「一芸に達するものは他芸にも通ずる」という考え方にもつながる。
嘉納もまた、この伝統に従い、柔術の稽古(個々の領域)から「精力善用・自他共栄」(人間そのものの究極的な境地)へとつながった。
柔道の技術上の研究からすべて武術というものについてこういうことを悟った。すなわち、何事もその目的をもっともよくなしとげようとすればその目的に向かって心身の力をもっとも有効に使用せねばならぬ、という宇内の大原則の一つの応用であるということである。
(中略)
この柔道を攻撃防御の仕方に応用したのが武術とよばれる。これを身体をよくすることに応用したるを体育と称し、知を研くに応用したるときにこれを知育といい、徳を養うに応用したるときは徳育ととなえる。衣食住、その他社会全般にも応用して、社会生活改善法、処世法、執務法、などといわるべきものになる。(嘉納・著作集第3巻141頁)
ポイントは、個々の領域の究極が人間そのものの究極につながると理解されることによって、個々の領域における努力が強力となり質的な深みをもってくる、という相良亨氏の次の指摘である。
その個々の領域の究極のありようが、単にその領域の究極の境地であるにとどまらず、同時に、宇宙・人間の究極的なるなにものかにつながると理解されはじめると、それは、人々の人間としての存在の根底にかかわるものとなり、その努力は強力なものとなり、質的な深みをもってくる(相良亨「日本の思想」70頁)
例えば、嘉納は、体育について、単なる体育として行うより、精神教育と関連して行ったほうが生徒は重んじるようになるというが、上記の指摘と同様の内容だろう。
かく道徳教育が体育から裨益を受けるように、体育も道徳教育から力を得ることも少なくない。体育を単純なる体育として課す時は権威が少ないが、大なる道と結び付け、精神教育と関連して施す時は、一段深い意義を感ずるようになって、体育そのものを重んずるようになる。(嘉納・著作集第3巻312頁)
話は多少脇にそれるが、マックス・ヴェーバーは、『プロテスタンディズムの倫理と資本主義の精神』において、西洋近代の資本主義発展の原動力がプロテスタントの宗教倫理にある、つまり、(単純化すると)商売(個々の領域)が神(宇宙・人間の究極的境地)につながると理解されたことによって、資本主義が発展したと指摘した。
上記の相良亨氏の指摘は、このマックス・ヴェーバーの指摘を想起させるが、同様に、近代の日本の発展の原因は、個々の領域の努力(例えば「ものづくり」の領域など)が人間の究極的な境地(人間的な修養)とつながっている、というこの「道」のコンセプトを国民が広く共有していたから、と説明できるだろうか。
身体から心へ
「道」に含まれる第二のコンセプトは、業の基本的な単位としての所作の仕方、すなわち「型」が重視され、この「型」を身につけることにより、「自由」「自由自在」「天人合一」などの境地に至る、というものである。単純化すると、「身体」から「心」に至るという考えである。
例えば、相良亨氏は、宮本武蔵の剣術における「型」と「自由」について次のようにいう。
彼は、太刀を「心の儘に」「自由にふる」こと、つまり「無理」なくふることを求め、その「心のきき」を体得させるために、太刀をふる簡単な二、三の動作のつながりである「五つのおもて」(表。基本形)を説いた。
これを稽古する時、太刀を「自由にふる」ことが身につくというものである。思うに、太刀はわれわれにとって異物である。異物を人間はおのずからの動きの中にだき込むのが武蔵の説く稽古鍛錬であるといえよう。
しかし、太刀は本来、天地の異物ではない。稽古鍛錬は太刀が本来異物でないことを体得させるものといえよう。太刀が異物ではないことを体得しえた時、その時その人はすでに天地のおずからなる「天理」におのずからはなれぬ「自由」の境地に悟入しているといえよう。(相良亨・日本の思想83頁)
例えば、茶道もまた同様である。足の運び、座り方や姿勢、茶碗の持ち方など一挙手一投足に定まった型があるが、その型を身につけることによって自由自在となる深い精神的な世界に至ると考えられている。
この「身体」から「心」に至る典型的なものは、いわゆる「礼」だろう。
江戸時代の儒学者である貝原益軒が著し、ベストセラーとなった育児書「和俗童子訓」には、「礼あれば、・・心も亦さだまりてやすし。」とあるが、教育学者である辻本雅史氏は、江戸時代の人々が、礼という「型」を通じて「心」を修養するという教育観を広く共有していたことを指摘している。
礼は天地のつねにして、人の則也。即人の作法をいへり。礼なければ、人間の作法にあらず。禽獣に同じ。故に幼きより、礼をつつしみて守るべし。人のわざ、事ごとに皆礼あり。よろづの事、礼あれば、すぢめよくして行われやすく、心も亦さだまりてやすし。(和俗童子訓)
(中略)
実はさらに重要なのは、その「礼」が外面の身体にとどまるだけではなく、「心も亦さだまりやすし」というように、人の心のあり方まで規定すると考えられていることです。つまり、人は「礼」によって心が安定し、正しく生きることができるというのです。
「礼」という一種の身体技法が、心を正しくするための回路である、というこの考え方は、先に見た益軒の「身体から心へ」向う教育観と通底しています。この論理は、一定の身体的な行動の型を日々実戦することが、心を修養することにつながるという思想を導き出すことになります。(辻本雅史「教育を「江戸」から考える 学び・身体・メディア」139頁)
この第二のポイントは次の通りである。
「道」が内包する第一のコンセプトとして、個々の領域の究極が人や宇宙の究極につながっているというものにふれたが、第二のコンセプトのポイントは、「個々の領域の究極」と「人や宇宙の究極」は、「型」や「身体」を回路としてつながっているという点である。
歴史学者である源了圓氏は、「なぜ日本人は「フォームとしての型」に特別の感情をもっているのだろうか。」、何故、日本人は「型」を真摯に学ぶのか、という問いを提出した上で、それは、「個々の型を通じて直覚された小宇宙は、大宇宙へとつながる。」と理解されているからであると指摘する。
型が右のような小宇宙であり、大宇宙への通路であること、少なくとも日本人がそのように考え、感じていること、このような事態を、鈴木大拙は次のように語っている。
「一芸の熟達に必要な、あらゆる実際的な技術や方法論的詳細の底には、自分の所謂る「宇宙的無意識」に直接到達する或直覚が存し、各種芸術に属する是等の諸直覚はすべてみな、個個無関聯な、相互に無関係なものと看做すべきものではなく、一つの根本的な直覚から生ずるものと、看做すべきものであると云うのである。」(『禅と日本文化』)。
これを「型」の問題と結びつけて、日本人の個々の型を通じての直覚の一つ一つは、相互に関連し合って、「宇宙的無意識」という根本的直覚に通じる、ということができるだろう。文節化された個々の型を通じて直覚された小宇宙は、大宇宙へとつながる。そしてそのことが日本人の『型』を学ぶ際の真摯さの原因であると思う。
日本人の長きに渉る芸修練の歴史の中で形成された型体得のパターンである「守・破・離」の『守る』の段階、すなわち、型を『まね』び、そして『まなぶ』ことの重視は、このように考えないと説明できない。(源了圓『型と日本文化』42~43頁)
同様に、辻本雅史氏は、宗教はその種類を問わず大抵身体的な苦行が課せられるが、それは何故なのか、と問うた上で、「身体」こそが自分が超越的で根源的な世界な世界につながるための回路であると理解されているからと指摘する。
宗教的な修行は、洋の東西を問わず、あるいは宗教の種別を問わず、たいてい激しい苦行が課せられています。ほとんど生命の極限にいたるほどの激しい身体的な修行が、なぜ必要なのでしょうか。
宗教によって、その説明の論理や言い方などは違うでしょう。しかし、激しい身体訓練のうちに、言葉で語られる理論や説明では届かない、深い精神世界に潜入し悟入する確かな回路がある、そう確信されている点では、共通しているのではないでしょうか。
宗教は、ある種の超越的な世界に悟入することを目指しています。すなわち、宗教的な超越の世界は、「心で考える」いわば言語的な過程を越えて、身体を回路とすることによって、はじめて悟入できるということに違いありません。
「身体」は、実はもっとも身近な「自然」です。また身体は「いのち」の「在処」、というよりもむしろ「いのち」のはたらきそのものにほかなりません。
「いのち」は一つ一つ個体として簡潔して存在する、あるいは一つの「いのち」はその個体の「持ち物」である、といった考え方をするのは、たぶん「近代人」だけでしょう。「いのち」は、それを生みだした「大いなる自然」の一部を構成するのです。このように考える思想の方が、歴史的にはるかに普遍的だと思います。
この意味で、儒学が前提とする「天地自然」は、「大いなる自然」であり「大いなるいのち」ととらえられます。そして人の「いのち」としての身体は、「天地自然」の一部を成している存在です。
とすれば、身近な「自然」としてのこの「身体」を回路とすることによって、人は、日常を超えた超越的かつ根源的な「いのち」(生命)にふれることができる、そう考えてよいでしょう。
そのように考えれば、「いのち」の在処であるこの「身体」こそ、自分が超越的で根源的な世界につながる接点にほかならないのです。(辻本雅史「教育を「江戸」から考える 学び・身体・メディア」145~146頁)
究極は修行そのものにある
最後に、その究極の境地は、彼方にあるのではなく、日々の修行そのものにある、というコンセプトにふれておきたい。
修行は悟りの手段ではなく、悟りそのものであるという、中世の禅僧、道元(道元 – Wikipedia)の「修証一等」に代表される考え方である。
「道」には、日本古来からのやまと言葉である「みち」と中国から渡来した「どう」があるが、相良亨氏は、「どう」には、究極的な境地のイメージがあるのに対し、「みち」には、たどり行くという営み、すなわち、「その時、たどりいく先の場所も、たどることによってたどり着くであろう場であり、ある方向この方向にある場であり、たどり着くまでは明確にならない場」としてイメージがあると指摘する。
そして、中国から渡来した「どう」とやまと言葉である「みち」が相互に影響を及ぼしあい、もともとの意味から変容した可能性を指摘し、中国の「道」との比較における日本の「道」の特色として、たどり行く営みの契機が重視されてきた傾向を指摘し、その例として道元の「修証一等」を挙げている(72~73)。
つまり、道元は、「道」を人や宇宙の究極の境地(「どう」)という意味で使いながらも、その思想の根本は、修行そのもの(「みち」たどり行く)が悟り(「どう」究極)である、という考え方であった。
確かに、「今」の個々の営みが「人間としての存在の根底にかかわるもの」と認識されるのであれば(第一のコンセプト)、未来にある何かではなく、今この瞬間瞬間における生が問われることになる。
また、人や宇宙の究極につながる回路が身体であるならば(第二のコンセプト)、今この瞬間しか身体を回路とすることはできない以上、修行しているときしか究極につながらないともいえる。
例えば、前回引用した望月氏が、以下のように「修行の本筋は日常の稽古にある。」と述べるとき、おそらくその背景には、日々の日常の稽古こそ究極そのものであるという考えがあるのではないだろうか。
そもそも柔道とは何か。単なる勝ち、負けを目的とするスポーツではなく、人格形成の教育を主体とするもので、精力善用とは、単なる畳の上だけではなく、人生各般にわたっての精力を善用することで、自他共栄という目的に向って最善活用する道である。
柔道修行法の中には「試合」があるが、これは目的ではなく、「味ずけ」調味料という程度のもので、修行の本筋は日常の稽古にある。
調味料の味がよいからといってこれを主食物の代りにすれば、結局逸脱するのである(この前段ではスポーツ選手の「ドーピングによる死」が述べられている。筆者注)。それでもスポーツ柔道は、道の柔道より進歩し、進化しているといえようか(望月稔、柔道新聞、昭和61年3月20日付4面)
このコンセプトのポイントは、二つある。
一つは、第一のポイントと一部重なるが、何かの目的達成の手段として学ぶのではなく、学びたいから学ぶ、という無条件無目的な学びの姿勢、すなわち、学ぶことに関する強烈なモチベーションと学ぶことそのものを喜びとする状態、いうなれば、心理学でいう「フロー」(フロー – Wikipedia)とでも評される状態があることである。
例えば、学校の勉強をするにしても、いい点数を取りたいから、よくない点だと叱られるから、いい学校に入りたいからなど、何らかの目的達成のために勉強するというケースが多い。しかし、このような条件付きの学びと、学ぶことそのものが面白いから学ぶというような無条件無目的な学びでは、学びの質や量に大きな差がでてくる。
二つ目は「引退」がないことである。
大統領となる前であるが、前ロシア大統領(現首相)のプーチン氏は、講道館にいってみたいと思い、訪問したという。そこで印象深い光景に出会う。
若い人、まだ子供の人たちが稽古をしていました。すると、そこにかなり年配の方が二人現れたのです。どのくらいの年齢だったかはわかりませんが、私には七十歳以上に見えました。
そして、丁寧に慎重にではありましたが、三十分ほど畳の上で稽古をしました。お互いを丁寧に投げることも何度かありました。
びっくりしました。まったく予想外でした。本当に印象深い光景で、柔道は一生続けていくことができるし、続けなければならないと思いました。(「プーチンと柔道の心」)
プーチン氏が見たものは、修行そのものが究極であるという日本の伝統的な柔道家の姿だったのではないだろうか。
(次回に続く)。
※本記事は、2010年8月から酒井重義(judo3.0)によってブログで連載された研究論考「勇者出処~嘉納治五郎の柔道と教育」の再掲です。